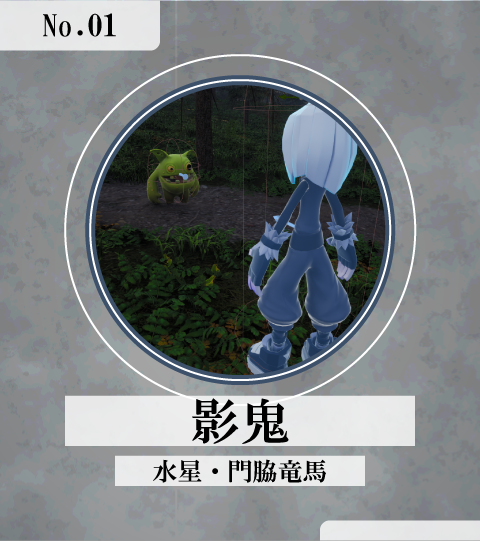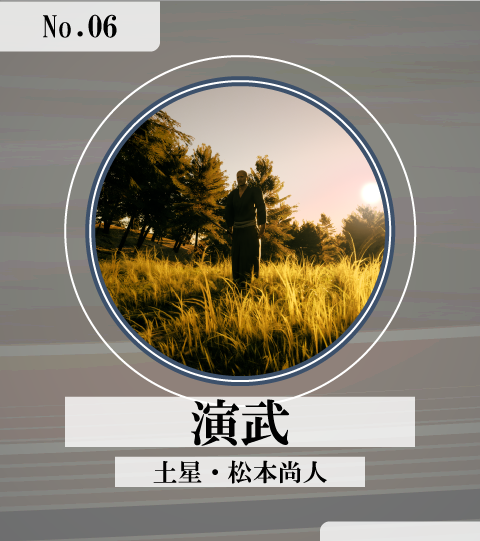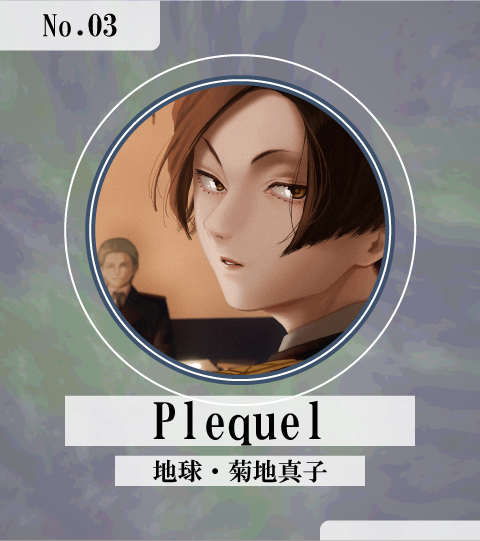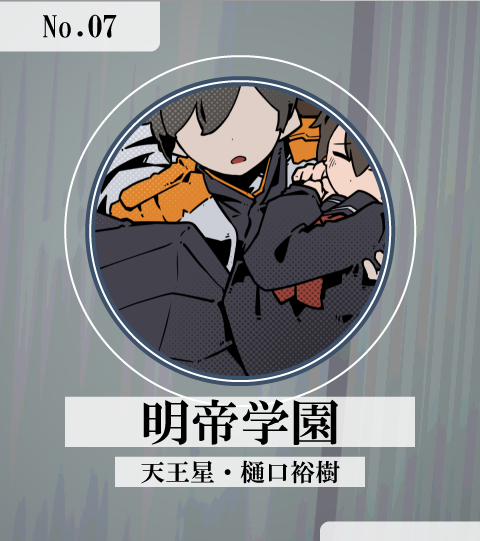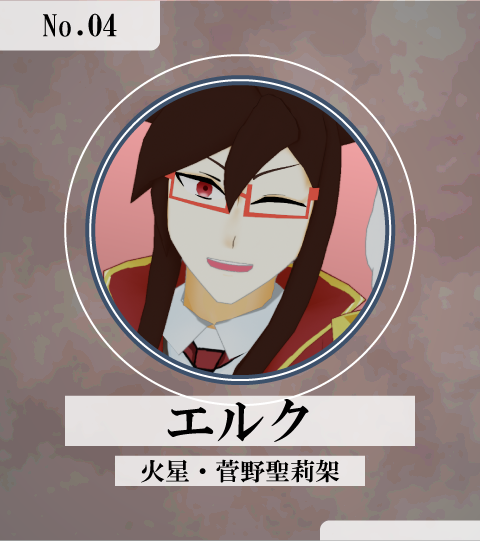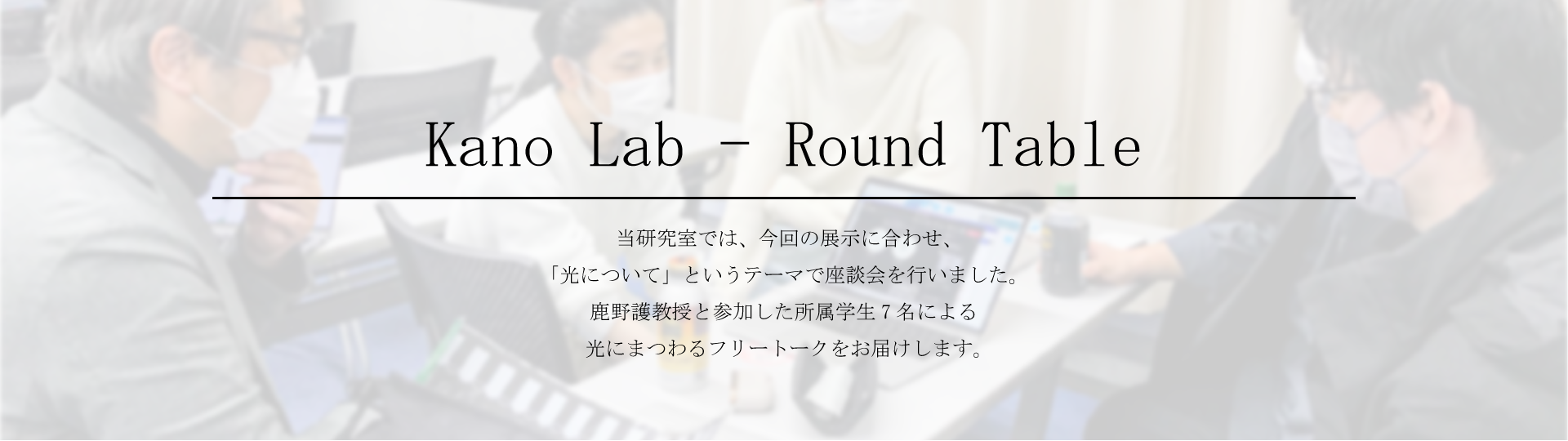
菊地真子(以下、菊地):制作に関連した光についての話で言うと、私は「自然光」へのこだわりがすごく強いですね。電気の光よりも長い時間見ていますし、私が元々南向きの家に住んでいたので、昼間電気を使うということがあまりなくて。それで、自然の光の美しさみたいなものが、子供の頃からずっと印象に残っていて、そこがこだわりになりました。いまでもCGの制作では、できる限り自然光の状態に近づけたいと考えながら制作をしていますね。
江﨑里琉(以下、江﨑):作品と光で言うと……意識して、というわけではないんですが、暗いのはあまり使わないというか、全体的に光が入っているほうが強いのかなと思いますね。自分の作品に関しては。自分が普段から暗いところにいるから、作品だけでも明るくしたいなというのがあるのかもしれないですね。
菊地:なるほど……作品を明るくすることで、自分も明るくなる、みたいな?
江﨑:ある種の入り込みじゃないけど、「自分はこうありたい」みたいなのを形にできるから、たぶんそっち側に反映させているのかなと。
菊地:それも面白いですね。
樋口裕樹(以下、樋口):「こうありたい姿」も光なのかもしれない、希望というか。
鹿野護(以下、鹿野):そうですね、「こうありたい」が光になっている可能性はありますね。だから、ものすごく大きな概念的なものとして光が、人間の脳の中には存在していて。表現だったり、いろいろなものにそれが反映しているということはあるかな、と思いますよ。
江﨑:個人的な好みですけど、夏の日差しの強さが好きなので、影の色と元の色がはっきり分かれているというか、コントラストが強めなのが好きですかね。
樋口:夏はいいよね。
江﨑:いいですね(笑)
菅野聖莉架(以下、菅野):季節によってコントラスト変わるの面白いよね。
菊地:光のコントラストだけでいうと、私は冬の方が強いイメージがありますね。光が拡散されていないから。
江﨑:確かに強さでいうと、冬の方が強いかも。私はそこに色とりどりな感じが加わっているのが好きなんだと。
菊地:確かに、夏は周りの彩りもあって綺麗に見えるみたいなところもあるんでしょうね。菅野さんは何かありますか?
菅野:なんだろう、こういうときにパッと出てこないんですが。太陽の出ている時間がちょっと興味があって、夏至とか冬至とか、あれを越えると”ああ、これから日の出ている時間が短くなるんだろうな”とか、”明日はもっと長くなるんだな、嬉しいな”みたいなことはよく、考えてますかね。太陽が出ている時間が長いと、嬉しかったりします。
樋口:嬉しいのか。……俺、嫌だな(笑) 俺は、日が出ている時間は集中ができなくて。太陽光が窓から入ってると、集中が切れるんですよ。だから、本当は学校も午後から始まってほしい(笑)
鹿野:じゃあ、太陽浴びながら作業……みたいなこともしない、ってこと?
樋口:しないですね。
門脇竜馬(以下、門脇):それはわかりますね。俺、いつもカーテン閉め切ってるんで。授業をオンラインで受けるとき。
江﨑・菅野:わかる(笑)
門脇:基本的に外の光が入らないようにしてますね。
鹿野:病まない?(笑)
門脇:作業しすぎて、時間があまりにも過ぎちゃって、自分の中の時間がわからなくなったら、外に出たりします(笑)
鹿野:そっか。みんな暗いところでやるの?
菊地:いや!私はもう、バリバリに太陽の下で作業しますよ。
鹿野:太陽の下で(笑)そうなんだ。逆に意外ですよね。
菊地:え?なんで?
鹿野:独自の世界にいる感じが……。
菊地:不服です、ちょっと(笑)
樋口:こっち側だと思ってた(笑)
伊藤弦(以下、伊藤):でも真子さんのZoom見ると、いつも太陽の光が綺麗なんですよね。
鹿野:たしかに!
菊地:そうそう(笑)そもそも蛍光灯があまり好きじゃなくて、うちでは置き型で暖色のライトしか使わないんですよ。それだと暗いから(笑)
鹿野:さっき”蛍光灯が苦手だ”って話が出ましたけど、大体カフェとか、ギャラリーとかって蛍光灯を使わないんですよね。ヨーロッパも使わないところが多い。なんでですかね?
菊地:太陽光は真っ白な光なので、蛍光灯のほうが近いとは思いますけどね。だからデッサン教室とか、たいてい蛍光灯ですよね。光の色が正しく見えるように。
鹿野:なんででしょうね、飲食店なんかが蛍光灯を使わないのは。逆に、家電量販店とかは真っ白じゃないですか。
樋口:家電量販店……でも、家電とかが黄ばんで見えたらいやじゃないですか?
全員:(笑)
鹿野:色がちゃんと見えるように?そうか。飲食店なんかだと、暖色の方が美味しく見えるからかもしれないですね?
門脇:それもあるでしょうし、オレンジっぽいと「炎」の光に近いので、たぶんそっちのほうが安心するんですよね。
鹿野:——良いこと言うね。
伊藤:そういえば、火について思い出したことがあって。「VRチャット(※バーチャル・リアリティ(仮想空間)のなかで人と交流できるゲーム)」に僕、よく居座っているんですけど……VRって、視覚の感覚しか基本的にないじゃないですか。なのに、VRのワールドの中で、焚き火とか暖炉があると、そこに皆が集まっていく傾向があって。
鹿野:ああ、”ゲームの中での炎”に。
伊藤:そうなんですよ。VRだから別に、暖かいとかそういうことでもないんですけど、何故か自然と皆こう……焚き火、暖炉のところに集まってくる。あと、こたつ。こたつも皆集まってきます。
樋口:前に(伊藤さんが)言ってなかったっけ。”VRを長くやっているとVRのなかで触られた感覚が伝わってくる”って。
鹿野:そうなの?
伊藤:そうです。僕にはその感覚があります。
鹿野:じゃあ、その感覚があるのであれば、VRのなかでも”炎”というメタファーが自然に人を寄せる可能性があると。
伊藤:そうだと思います。
鹿野:そういえば、言葉と光の話をしたくて。言葉の中に光の表現が出てくるんですよ。「輝く」とか。それって、モノの輝きだけじゃなくて、「君、輝いてるね」とか、真相が「明らかになる」とか。実は光って、人間の思考の中にすごく入っているんじゃないかなと。光に関する言葉表現を、実はものすごく使っている。それが現象とか表現の光じゃなくて、人間の未来みたいなものになっていると思うと、「次の日朝日が出てくる」というすごくシンプルな現象と思考がものすごく結びついていて、そこからはたぶん、生命は逃れられないというか。……そういうのが好き。
全員:(笑)
門脇:視界がはっきりするという比喩としてそれが使われているんでしょうね。たとえば、電球もそうじゃないですか。思いついたとか、そういうときに電球がつく表現。
樋口:そもそも「閃く」って、光だし。
菊地:確かに。
鹿野:なんでだろうね。
門脇:見えなかったものが見えるっていう、比喩として使っているんじゃないかな。
菊地:だからさ、基本的にはさ。「闇」なんじゃないですか。
鹿野:基本的には「闇」?
菊地:そう、基本的に、世界が”闇”なんですよ。
樋口:なるほど?(笑)
菊地:そこに、光がパッて点く、っていう状態が、「明るみに出る」とか「白日の下に晒される」とか。
樋口:世界が暗黒ベースっていうのは、そうかも。全部明るくて、そこから暗黒が生まれるってことはないから……。最初から全部暗くて、そこに光が。
菊地:だから、そう。キリスト教のまさに、「光あれ」だよね。ヤハウェの最初の言葉、光あれ。
全員:(笑)
鹿野:それから、視神経の話をしたいんですが、いいですか?
菊地:いいですよ。
全員:(笑)
鹿野:視神経って、眼球の周りにいっぱいついているんですけどね。色を見分ける視神経と、光を見分けるものには圧倒的な差があって、10倍くらい光の方が多いんですよ。色はあまり見分けられないけど、光の明度差は見分けられるんです。だから、もしかすると人は、色よりも光をものすごく重要な情報として見ているんじゃないかと。
樋口:へえ。
鹿野:それから、目って微振動してるんですよ。常にブルブル震えてて、それでスキャンしているんです。ピントの合う距離ってすごく小さいんですよ、10円玉くらい。だから、超高速に無意識にスキャンして、それを脳がコラージュしているという考え方があるんですけど。だから、光も見えているのは本当に一部で、それ以外は脳内合成、または想像で補填している。と考えると、光を見ていると言いつつも、実は想像、疑似的なものが大半っていう可能性があるんです。サッカディック・サプレッションっていうんですけど。そう考えると光って実は、見ていると言うけど脳にある。色もそうです。要するに、光があるんじゃなくて、光を脳内で作り出している、認識しているんだと。
松本:デッサンとかで、よく見たら別物になってしまっている、みたいなことはありますね。ちゃんと見ているはずなのに、よく見ると現実と描いたものが違う。技量とは別になんか、ズレている気がします。
樋口:脳が勝手に補完して勝手に描かれている、みたいな。
鹿野:あともう一つが、視野の情報量ってとてつもない情報量なんですよ。それを脳が一瞬で処理できるわけがない。そのときに面白い考え方が、人間は「光が上からくる」という前提のもと、余計な情報を全部キャンセルしていると。だから、トリックアートに騙されるという説があったりとか。
伊藤:ああ。
鹿野:あと、ドロップシャドウをつけると、浮いているように見えるとか。実は表現って、光が上からきているという人間の、本能的なキャンセル・ごまかしを、うまく使っているという考え方があって。そうすると、「表現ってなんだろう」って。人間が持っている認識の適当な部分とか、キャンセルしている部分を上手く理解して、突いてくる。それが表現でやっていることなのかな、と思ったりします。考えれば考えるほど、認識の方に何かが起きているというか。
菊地:光があるというよりは、「光があるという事実」自体を認識している、という感じですよね。
鹿野:そうそう。そういうのに、いつも……モヤモヤ……。
菊地:モヤモヤしてる?(笑)
鹿野:しないか(笑)
全員:しないです(笑)
鹿野:何かをキャンセルしているんですよ、脳が。だから、結果的にリアルに見えるとか、可愛く見えるとか、〇〇調に見えるとかっていうのは、そういうものを作り手たちが本能的に使っているとしか僕は思えない。そこを突いてきているから、「かわいい」とか、「ああ、これはすごく巨大なものだ」とか。そういうふうに見える。
菊地:私の父、設計の仕事をしているんですけど。昔、仕事の上司から言われたのが、「木は灰色だ」という話で。木は本来灰色なんだけど、茶色のように思うのは、そちらに慣れているからだと。それ以来、そのことを意識して仕事をするようになったと言っていました。だからそういう、色の見え方とか、経験で判断するみたいなところがあるんでしょうね。周りに茶色に色づけられた木材があると、そうだと思ってしまうけど、実際に見ると灰色だという違いに気づく。
鹿野:そうですね。表現を学ぶって、そのメカニズムに近づいていくっていうことなんでしょうね。本当はグレーなんだという理解ができる。解像度が上がっていくというか。
菊地:光とかも結局、実際によく見て、そういった現象一つひとつを追っている人が描写力高くなっていくんだろうなという感じがしますよね。CGとか見ていても、そういう人たちの光に対する意識の高さって全然違う。
鹿野:CG学びたての頃に、レストランで出てくるグラスと、光。反射するじゃないですか。「これどうなってるんだろう?」って思いません?CG学びたての頃ってさ、これどうやったら作れるだろう?って。あとアンビエントオクルージョンとか、モノとモノとの接地の暗さ?そういうものとかもすごく目に入ってくるようになりますよね。一回表現を経験すると、そのアンテナがもう立っちゃうから、入ってくるようになる。だから、作る最大の醍醐味はそこですよね。世界を知る、チャンネルを開いていく。それを全部キャンセルして、例えばアセットだったりAIを使って作ると、そこが手に入らないから、作る面白さはそこにはあまりない可能性がありますよね。
菊地:作ることで知る。
鹿野:作ることで知るし、その「知る」が実は、生きる目的だったりすると、そこが醍醐味なんですよね。
——2022/12/20 鹿野研究室座談会より
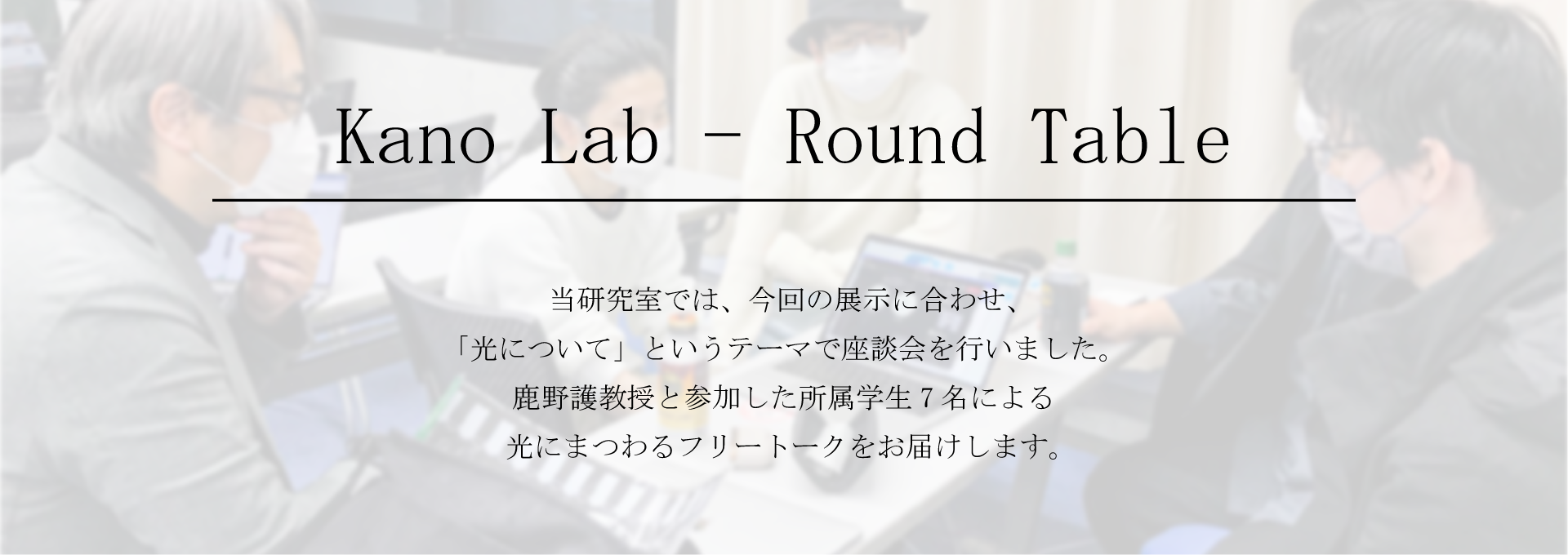
菊地真子(以下、菊地):制作に関連した光についての話で言うと、私は「自然光」へのこだわりがすごく強いですね。電気の光よりも長い時間見ていますし、私が元々南向きの家に住んでいたので、昼間電気を使うということがあまりなくて。それで、自然の光の美しさみたいなものが、子供の頃からずっと印象に残っていて、そこがこだわりになりました。いまでもCGの制作では、できる限り自然光の状態に近づけたいと考えながら制作をしていますね。
江﨑里琉(以下、江﨑):作品と光で言うと……意識して、というわけではないんですが、暗いのはあまり使わないというか、全体的に光が入っているほうが強いのかなと思いますね。自分の作品に関しては。自分が普段から暗いところにいるから、作品だけでも明るくしたいなというのがあるのかもしれないですね。
菊地:なるほど……作品を明るくすることで、自分も明るくなる、みたいな?
江﨑:ある種の入り込みじゃないけど、「自分はこうありたい」みたいなのを形にできるから、たぶんそっち側に反映させているのかなと。
菊地:それも面白いですね。
樋口裕樹(以下、樋口):「こうありたい姿」も光なのかもしれない、希望というか。
鹿野護(以下、鹿野):そうですね、「こうありたい」が光になっている可能性はありますね。だから、ものすごく大きな概念的なものとして光が、人間の脳の中には存在していて。表現だったり、いろいろなものにそれが反映しているということはあるかな、と思いますよ。
江﨑:個人的な好みですけど、夏の日差しの強さが好きなので、影の色と元の色がはっきり分かれているというか、コントラストが強めなのが好きですかね。
樋口:夏はいいよね。
江﨑:いいですね(笑)
菅野聖莉架(以下、菅野):季節によってコントラスト変わるの面白いよね。
菊地:光のコントラストだけでいうと、私は冬の方が強いイメージがありますね。光が拡散されていないから。
江﨑:確かに強さでいうと、冬の方が強いかも。私はそこに色とりどりな感じが加わっているのが好きなんだと。
菊地:確かに、夏は周りの彩りもあって綺麗に見えるみたいなところもあるんでしょうね。菅野さんは何かありますか?
菅野:なんだろう、こういうときにパッと出てこないんですが。太陽の出ている時間がちょっと興味があって、夏至とか冬至とか、あれを越えると”ああ、これから日の出ている時間が短くなるんだろうな”とか、”明日はもっと長くなるんだな、嬉しいな”みたいなことはよく、考えてますかね。太陽が出ている時間が長いと、嬉しかったりします。
樋口:嬉しいのか。……俺、嫌だな(笑) 俺は、日が出ている時間は集中ができなくて。太陽光が窓から入ってると、集中が切れるんですよ。だから、本当は学校も午後から始まってほしい(笑)
鹿野:じゃあ、太陽浴びながら作業……みたいなこともしない、ってこと?
樋口:しないですね。
門脇竜馬(以下、門脇):それはわかりますね。俺、いつもカーテン閉め切ってるんで。授業をオンラインで受けるとき。
江﨑・菅野:わかる(笑)
門脇:基本的に外の光が入らないようにしてますね。
鹿野:病まない?(笑)
門脇:作業しすぎて、時間があまりにも過ぎちゃって、自分の中の時間がわからなくなったら、外に出たりします(笑)
鹿野:そっか。みんな暗いところでやるの?
菊地:いや!私はもう、バリバリに太陽の下で作業しますよ。
鹿野:太陽の下で(笑)そうなんだ。逆に意外ですよね。
菊地:え?なんで?
鹿野:独自の世界にいる感じが……。
菊地:不服です、ちょっと(笑)
樋口:こっち側だと思ってた(笑)
伊藤弦(以下、伊藤):でも真子さんのZoom見ると、いつも太陽の光が綺麗なんですよね。
鹿野:たしかに!
菊地:そうそう(笑)そもそも蛍光灯があまり好きじゃなくて、うちでは置き型で暖色のライトしか使わないんですよ。それだと暗いから(笑)
鹿野:さっき”蛍光灯が苦手だ”って話が出ましたけど、大体カフェとか、ギャラリーとかって蛍光灯を使わないんですよね。ヨーロッパも使わないところが多い。なんでですかね?
菊地:太陽光は真っ白な光なので、蛍光灯のほうが近いとは思いますけどね。だからデッサン教室とか、たいてい蛍光灯ですよね。光の色が正しく見えるように。
鹿野:なんででしょうね、飲食店なんかが蛍光灯を使わないのは。逆に、家電量販店とかは真っ白じゃないですか。
樋口:家電量販店……でも、家電とかが黄ばんで見えたらいやじゃないですか?
全員:(笑)
鹿野:色がちゃんと見えるように?そうか。飲食店なんかだと、暖色の方が美味しく見えるからかもしれないですね?
門脇:それもあるでしょうし、オレンジっぽいと「炎」の光に近いので、たぶんそっちのほうが安心するんですよね。
鹿野:——良いこと言うね。
伊藤:そういえば、火について思い出したことがあって。「VRチャット(※バーチャル・リアリティ(仮想空間)のなかで人と交流できるゲーム)」に僕、よく居座っているんですけど……VRって、視覚の感覚しか基本的にないじゃないですか。なのに、VRのワールドの中で、焚き火とか暖炉があると、そこに皆が集まっていく傾向があって。
鹿野:ああ、”ゲームの中での炎”に。
伊藤:そうなんですよ。VRだから別に、暖かいとかそういうことでもないんですけど、何故か自然と皆こう……焚き火、暖炉のところに集まってくる。あと、こたつ。こたつも皆集まってきます。
樋口:前に(伊藤さんが)言ってなかったっけ。”VRを長くやっているとVRのなかで触られた感覚が伝わってくる”って。
鹿野:そうなの?
伊藤:そうです。僕にはその感覚があります。
鹿野:じゃあ、その感覚があるのであれば、VRのなかでも”炎”というメタファーが自然に人を寄せる可能性があると。
伊藤:そうだと思います。
鹿野:そういえば、言葉と光の話をしたくて。言葉の中に光の表現が出てくるんですよ。「輝く」とか。それって、モノの輝きだけじゃなくて、「君、輝いてるね」とか、真相が「明らかになる」とか。実は光って、人間の思考の中にすごく入っているんじゃないかなと。光に関する言葉表現を、実はものすごく使っている。それが現象とか表現の光じゃなくて、人間の未来みたいなものになっていると思うと、「次の日朝日が出てくる」というすごくシンプルな現象と思考がものすごく結びついていて、そこからはたぶん、生命は逃れられないというか。……そういうのが好き。
全員:(笑)
門脇:視界がはっきりするという比喩としてそれが使われているんでしょうね。たとえば、電球もそうじゃないですか。思いついたとか、そういうときに電球がつく表現。
樋口:そもそも「閃く」って、光だし。
菊地:確かに。
鹿野:なんでだろうね。
門脇:見えなかったものが見えるっていう、比喩として使っているんじゃないかな。
菊地:だからさ、基本的にはさ。「闇」なんじゃないですか。
鹿野:基本的には「闇」?
菊地:そう、基本的に、世界が”闇”なんですよ。
樋口:なるほど?(笑)
菊地:そこに、光がパッて点く、っていう状態が、「明るみに出る」とか「白日の下に晒される」とか。
樋口:世界が暗黒ベースっていうのは、そうかも。全部明るくて、そこから暗黒が生まれるってことはないから……。最初から全部暗くて、そこに光が。
菊地:だから、そう。キリスト教のまさに、「光あれ」だよね。ヤハウェの最初の言葉、光あれ。
全員:(笑)
鹿野:それから、視神経の話をしたいんですが、いいですか?
菊地:いいですよ。
全員:(笑)
鹿野:視神経って、眼球の周りにいっぱいついているんですけどね。色を見分ける視神経と、光を見分けるものには圧倒的な差があって、10倍くらい光の方が多いんですよ。色はあまり見分けられないけど、光の明度差は見分けられるんです。だから、もしかすると人は、色よりも光をものすごく重要な情報として見ているんじゃないかと。
樋口:へえ。
鹿野:それから、目って微振動してるんですよ。常にブルブル震えてて、それでスキャンしているんです。ピントの合う距離ってすごく小さいんですよ、10円玉くらい。だから、超高速に無意識にスキャンして、それを脳がコラージュしているという考え方があるんですけど。だから、光も見えているのは本当に一部で、それ以外は脳内合成、または想像で補填している。と考えると、光を見ていると言いつつも、実は想像、疑似的なものが大半っていう可能性があるんです。サッカディック・サプレッションっていうんですけど。そう考えると光って実は、見ていると言うけど脳にある。色もそうです。要するに、光があるんじゃなくて、光を脳内で作り出している、認識しているんだと。
松本:デッサンとかで、よく見たら別物になってしまっている、みたいなことはありますね。ちゃんと見ているはずなのに、よく見ると現実と描いたものが違う。技量とは別になんか、ズレている気がします。
樋口:脳が勝手に補完して勝手に描かれている、みたいな。
鹿野:あともう一つが、視野の情報量ってとてつもない情報量なんですよ。それを脳が一瞬で処理できるわけがない。そのときに面白い考え方が、人間は「光が上からくる」という前提のもと、余計な情報を全部キャンセルしていると。だから、トリックアートに騙されるという説があったりとか。
伊藤:ああ。
鹿野:あと、ドロップシャドウをつけると、浮いているように見えるとか。実は表現って、光が上からきているという人間の、本能的なキャンセル・ごまかしを、うまく使っているという考え方があって。そうすると、「表現ってなんだろう」って。人間が持っている認識の適当な部分とか、キャンセルしている部分を上手く理解して、突いてくる。それが表現でやっていることなのかな、と思ったりします。考えれば考えるほど、認識の方に何かが起きているというか。
菊地:光があるというよりは、「光があるという事実」自体を認識している、という感じですよね。
鹿野:そうそう。そういうのに、いつも……モヤモヤ……。
菊地:モヤモヤしてる?(笑)
鹿野:しないか(笑)
全員:しないです(笑)
鹿野:何かをキャンセルしているんですよ、脳が。だから、結果的にリアルに見えるとか、可愛く見えるとか、〇〇調に見えるとかっていうのは、そういうものを作り手たちが本能的に使っているとしか僕は思えない。そこを突いてきているから、「かわいい」とか、「ああ、これはすごく巨大なものだ」とか。そういうふうに見える。
菊地:私の父、設計の仕事をしているんですけど。昔、仕事の上司から言われたのが、「木は灰色だ」という話で。木は本来灰色なんだけど、茶色のように思うのは、そちらに慣れているからだと。それ以来、そのことを意識して仕事をするようになったと言っていました。だからそういう、色の見え方とか、経験で判断するみたいなところがあるんでしょうね。周りに茶色に色づけられた木材があると、そうだと思ってしまうけど、実際に見ると灰色だという違いに気づく。
鹿野:そうですね。表現を学ぶって、そのメカニズムに近づいていくっていうことなんでしょうね。本当はグレーなんだという理解ができる。解像度が上がっていくというか。
菊地:光とかも結局、実際によく見て、そういった現象一つひとつを追っている人が描写力高くなっていくんだろうなという感じがしますよね。CGとか見ていても、そういう人たちの光に対する意識の高さって全然違う。
鹿野:CG学びたての頃に、レストランで出てくるグラスと、光。反射するじゃないですか。「これどうなってるんだろう?」って思いません?CG学びたての頃ってさ、これどうやったら作れるだろう?って。あとアンビエントオクルージョンとか、モノとモノとの接地の暗さ?そういうものとかもすごく目に入ってくるようになりますよね。一回表現を経験すると、そのアンテナがもう立っちゃうから、入ってくるようになる。だから、作る最大の醍醐味はそこですよね。世界を知る、チャンネルを開いていく。それを全部キャンセルして、例えばアセットだったりAIを使って作ると、そこが手に入らないから、作る面白さはそこにはあまりない可能性がありますよね。
菊地:作ることで知る。
鹿野:作ることで知るし、その「知る」が実は、生きる目的だったりすると、そこが醍醐味なんですよね。
——2022/12/20 鹿野研究室座談会より